みなさんこんにちは、リハノワのかわむーです!
今回は、千葉県鴨川市にある亀田総合病院で呼吸領域のリハビリテーションに携わる、理学療法士で米国呼吸療法士の鵜澤吉宏さんにお話を伺いました。
この記事では、鵜澤さんが情熱を注ぐ呼吸療法とリハビリテーションや、集中治療室での取り組みについてご紹介します。
※ 亀田メディカルセンターリハビリテーション部門の紹介記事はこちら
理学療法士・鵜澤吉宏さん

◆ 鵜澤吉宏 (うざわ・よしひろ)さん
亀田総合病院リハビリテーション事業管理部 理学療法士 / 米国呼吸療法士 / 肺機能検査技師 / 新生児・乳児専門呼吸療法士
千葉県出身。群馬大学医療技術短期大学部(現:群馬大学医学部保健学科)を卒業後、理学療法免許を取得し、1991年に亀田総合病院入職。1998年にオハイオ州立トレド大学呼吸療法学科に進学し、呼吸療法について学ぶ。2001年に米国呼吸療法士、肺機能検査技師、新生児/乳児専門呼吸療法士を取得し、亀田総合病院へ復職。2007年に横浜市立大学大学院修士課程を修了、2011年に東京大学大学院医学研究科を修了。呼吸ケアチームなど、呼吸療法に関連する事業に力を注ぐ。

実は、私は亀田病院で新卒から4年間勤務し、その間に鵜澤さんから多くのご指導をいただきました。当時、集中治療室(Intensive Care Unit:ICU)でのリハビリテーションに携わりながら、鵜澤さんの背中を追いかけて学んだ日々は、今でも忘れられない大切な思い出です。このようなご縁もあり、今回のインタビューには特別な思いがあります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
さて、現在は、呼吸や集中治療領域でのリハビリテーションをけん引する存在としてご活躍されている鵜澤さんですが、理学療法士を目指されたきっかけは何だったのでしょうか? 亀田総合病院に入職された当時のエピソードなども、ぜひお聞かせいただけると嬉しいです。
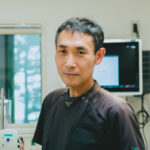
私が理学療法士という仕事を知ったのは、高校時代に読んだ旺文社の雑誌がきっかけでした。当時、学校に毎月届けられるその雑誌には職業紹介のページがあって、そこで初めて「理学療法士」という言葉を目にしたのです。
その頃、理学療法士という職業はまだあまり知られていなくて、私の周りにも関わりのある人はいませんでした。でも、だからこそ「まだ誰もやっていない仕事なのかも」と興味をもったのを覚えています。
また、姉が歯科衛生士だったこともあり、医療分野への興味はどこか心の中にあったのだと思います。それに加えて、体育会系で運動が好きだった私にとって、理学療法士の仕事はとても魅力的に映りました。
亀田病院とのご縁は、学生時代の臨床実習です。最初に指導してもらったのは、現リハビリ事業部の村永部長(当時主任)でした。しかし、実習が始まって2~3週間後に村永部長が長期研修に行くことになり、その後は当時のリハビリ室長である渡辺京子先生が引き継いで指導してくれました。
渡辺先生は、第1回理学療法士国家試験に合格し、日本の理学療法士の道を切り拓かれてきた方です。亀田のリハビリ事業部を築き上げ、誰もが一目置く存在でした。愛のある厳しいご指導をいただいたことは、とてもありがたい思い出です。
そんな渡辺先生にとって、私が最後の学生だったと伺ったときは、なんだか感慨深いものがありました。

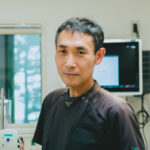
就職先は、千葉県出身で馴染みがあったことや実習を通じて感じた安心感が決め手となり、亀田病院を希望しました。
入職当時のリハビリ室は、理学療法士が8人、作業療法士や言語聴覚士を合わせても12~13人ほどの小さなチームでしたが、まるで大家族のような温かい雰囲気に包まれていました。
渡辺先生は「親分」のような存在で、そのもとに集まった仲間たちはみんな「兄弟」のように仲が良く、助け合いながら切磋琢磨する日々はとても充実していました。
当時はリハビリ科の医師がいない環境でしたが、オーダーがあればどんな相談にも対応するのが私たちのスタイルでした。私は、1年目は整形外科の患者さんを中心に多くの経験を積ませていただきました。
初めての学会発表では、膝内側側副靱帯損傷の患者さんに対する理学療法の報告を行いました。緊張しながらも全力で取り組んだ、忘れられない思い出です。

呼吸リハビリの世界へ

呼吸リハのスペシャリストとしてご活躍されているイメージが強かったので、最初の症例報告が整形外科の患者さんだったと伺い、新鮮に感じました。
鵜澤さんが呼吸リハに興味をもたれたのは、どのようなきっかけだったのでしょうか?
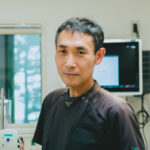
呼吸リハに興味を持つようになったのは、入職して間もない頃のことです。そのきっかけは、亀田病院で行われた1日半の研修会でした。
呼吸リハの最前線で活躍されていた宮川哲夫先生が、アメリカ留学から帰国された直後に亀田病院で研修会を開いてくださったんです。先生は最新の知識と技術を教えてくださり、その中で、私が担当していたCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の患者さんについて相談する機会もいただきました。
その患者さんは気管切開をして人工呼吸器を装着されており、当時の私は毎回緊張しながら対応していました。人工呼吸器のアラームが鳴るたびに看護師さんが駆けつけて吸引をしてくださるのですが、そのたびに「また迷惑をかけてしまったな」と冷や汗をかきながら診療していました。
そんな中、宮川先生が患者さんの血ガスデータを見ながらさらりと一言。「これはCOPDの急性増悪で、代償性呼吸性アシドーシスだね」。その瞬間、私は衝撃を受けました。数値を見ただけで患者さんの状態を的確に把握し、冷静に説明する姿に感動したのです。
さらに、先生は人工呼吸器を前にしても冷静で、「こうすればいいんだよ」「ここをこう調整すればもっと良くなるよ」と次々と対応策を示してくださったのです。その一つひとつの動きがまるで魔法のようで、私は思わず見入ってしまいました。
「自分もこんなふうになりたい!」とその時抱いた憧れは、いまでも私の中で鮮明に残っています。

私も初めて人工呼吸器の患者さんを担当させていただいたときのことを思い出しました。毎回緊張しながらリハビリに取り組んでいたのを覚えています。そして、鵜澤さんが冷静に人工呼吸器を操作しながら、ICUでのリハビリテーションのすすめ方を教えてくださった姿が、とても印象に残っています。
鵜澤さんが呼吸リハに取り組み始めた当時、どのようなことを行われていたのでしょうか?
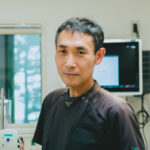
当時の「呼吸リハ」といえば、排痰やバイブレーション、腹式呼吸、タッピングなど、いまとは少し異なる手法が主流でした。
振り返ってみると、技術や知識の面ではまだ発展途上の時期でしたが、それでも患者さんにとって最善の支援を届けたい一心で、新しいことを学びながら全力で向き合っていました。
ちょうど私が2年目を迎える頃、呼吸領域を担当されていた先輩が退職されることになりました。
「次に誰が呼吸領域を中心的に担当する?」という話が出たとき、私は迷わず手を挙げました。これが、呼吸領域のリハビリテーションに本格的に携わるきっかけとなりました。

アメリカでの挑戦

呼吸領域のリハビリテーションはどのように学ばれていったのでしょうか?
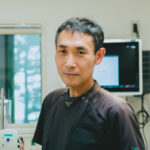
3学会合同呼吸療法認定士の試験を受験しました。これを勉強して資格を取得すれば、日々の臨床での悩みは解決するだろうと思ったのです。
しかし、資格を取ってみても現実はさほど変わりませんでした。人工呼吸器の設定の意味は分からず、アラームが鳴ったら冷や汗タラタラ。(当時はまだ)吸引もできない。結局、看護師さんを頼ることが多く「これじゃいけない」と痛感しました。
そんなとき、憧れていた宮川先生から「鵜澤くん、アメリカに行ってみなよ」と背中を押すような言葉をいただきました。
「自分が普段やっていることは本当に正しいのか?」「もっと良い方法があるのではないか?」その答えを見つけたい一心で、私はアメリカで呼吸療法を学ぶことを決意しました。

宮川先生の一言が、鵜澤さんの人生を大きく動かすきっかけになったのですね。
実際にアメリカで学ぶまでの道のりは、簡単なものではなかったと思います。どのような準備を経て渡米に至ったのか、そして留学中はどのような生活を送られたのか、ぜひお聞かせいただきたいです。
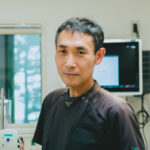
準備には3年ほどかかりました。まずはお金を貯めるところからのスタートです。当時、アメリカへの留学には年間500〜600万円ほど必要でした。私は州立大学を選んだため、費用をある程度抑えることができましたが、それでも年間200〜300万円は必要でした。貯金を続けながら、着実に準備を進めていきました。
そして1998年、理学療法士として8年目を迎えた年に、ついに渡米が実現。オハイオ州立トレド大学呼吸療法学科に進学し、本格的に呼吸療法を学ぶ日々がスタートしました。
アメリカには合計で3年半滞在しました。本来なら4年かかるプログラムでしたが、日本で取得した単位を認めてもらう「トランスファー」という制度を活用し、短縮することができました。また、専門科目についてはテストを受け、既に知識があることを証明することで一部免除を受けました。
これらの制度のおかげで、効率よく学びを進めることができましたが、それでも実習は6回行う必要があり、最低限3年は必要でした。
クラスメイトは基本的にアメリカ人が中心で、留学生はいませんでしたが、アフリカ系・ラテン系・中東系のルーツをもつ人々や、幅広い年代の仲間が集まっていました。中には母親世代の方や孫がいる方もおり、多様な背景を持つ人々と一緒に学ぶことができたのは、とても貴重な経験でした。
規定プログラム終了後、国家試験にも無事合格し、米国呼吸療法士、肺機能検査技師、新生児/乳児専門呼吸療法士の免許を取得。しばらくトレド市内の病院勤務やアメリカ国内で卒後研修や施設見学などをして、2001年に日本へ帰国しました。

帰国後の取り組み

アメリカでの学びを経て、日本へ帰国された後には、どのような活動に取り組まれたのでしょうか? 呼吸療法の知識を現場でどのように活かしていかれたのか、ぜひ教えてください。
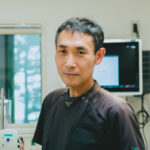
帰国後は、人工呼吸器を装着された患者さんや呼吸器疾患の患者さんのリハビリテーションに加え、スタッフ教育にも力を注ぎました。
当時、ICUでのリハビリテーションはまだ十分に確立していませんでしたが、多職種と連携しながらチームとしての取り組みを進めていきました。2018年の診療報酬改定で「早期離床・リハビリテーション加算」が導入されたことが追い風となり、ICUでの早期離床とリハビリテーションが普及していったのは大きな転機でした。
スタッフ教育では、日々の症例検討やICUでの診療同行に加え、呼吸療法認定士の資格取得を目指すスタッフ向けの勉強会を開催しました。アメリカ留学中、先生方の教え方がとても上手で、英語での授業ながらも理解しやすかった経験があり、「教え方を学ぶ」という視点を得たことは大きな収穫でした。そのため、帰国後はアメリカで得た知識や学びを、少しでもスタッフに還元できればという思いで教育に取り組みました。
また、院内の呼吸ケアチーム(Respiratory Support Team:RST)の活動にも力を入れました。当時、人工呼吸器の使用について、現場で共有されている知識や技術にはまだ課題が多いと感じており、患者さんに最適なケアを提供するためには、多職種が連携し、スキルを高め合う仕組みが必要だと考え、多職種での活動を始めました。
たまたま活動を始めた後、2010年に呼吸ケアチーム加算が導入されたことで、活動を継続できる基盤が整い、さらに取り組みを進めることができました。

ICUリハビリのこれから

ご紹介いただいた院内でのさまざまな活動に加え、院外では、研修会の開催や執筆活動等も積極的に行い、ICUの早期離床・リハビリテーションの文化を第一線で築き上げられてきたかと思います。
そんな鵜澤さんの豊富なご経験を踏まえ、これからのICUのリハビリテーションにおいて、特にセラピストに求められるスキルや役割について、どのようにお考えでしょうか?
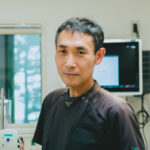
ICUでは、これまで見えなかったものが次々と「見える化」される時代になってきました。その進化に伴い、これからのセラピストには、これらを活用し、より精密な評価や効果的な治療を行うスキルが求められると感じています。
たとえば、人工呼吸器も、昔はただ空気を送るだけのものでしたが、今ではグラフィック波形を見て呼吸状態を詳しく評価できるようになりました。また、エコーを使えば大腿四頭筋の厚さが評価でき、無気肺や横隔膜の動きまでリアルタイムで観察できるようになりました。
さらに、肺の状態を連続的にモニタリングできる機械も登場しており、これまで手探りで行っていた部分が、より明確に視覚的に捉えられるようになっています。
こうした技術の進化とともに、ICUのリハビリテーションは大きく変わりつつあります。セラピストたちは、新しい知識や技術を柔軟に取り入れ、患者さんにとって最適なケアを提供できるよう進化し続けることが重要だと考えます。

技術の進化とともにリハビリテーションがどのように変化し、広がっていくのか、これからがとても楽しみです。
長年、リハビリテーションの現場で患者さんと向き合い、教育にも携わってこられた鵜澤さんですが、「リハビリテーション」とは、どのようなものだとお考えでしょうか? また、実践するうえで大切にしていることについても、ぜひ教えてもらえると嬉しいです。
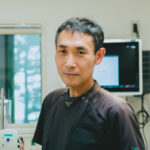
リハビリテーションとは、単に身体の回復を目指すだけではありません。最近、私はそれを「しなやかさを育む」ことだと捉えるようになりました。
「しなやかさ」とは、心理学でいう「レジリエンス」、すなわち新しい環境や変化に柔軟に対応し、前へ進む力のことです。
たとえば、病気や障害を抱えたり、心が傷ついてしまったりしたとき。どんな衝撃があっても柳がしなやかで折れないように、対象者の方が、少しずつ「自分らしさ」を取り戻し、変化し続ける人生のなかでより良い方向に導けるよう支えること。それが、リハビリテーションではないかと考えています。
もちろん教科書的なリハビリテーションは学んできましたが、いまはその枠を超え、こうした視点を持ちながらリハビリテーションを考え、提供していくことが大切だと思っています。

リハビリに励む方へメッセージ

最後に、ICUでリハビリテーションに取り組まれる当事者の方々へ、鵜澤さんからぜひメッセージをお願いできますでしょうか。
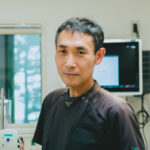
患者さんやご家族にとって、ICUでの時間はとても大きな不安や戸惑いを伴うものだと思います。私たちがリハビリに伺っても、モニターや点滴、人工呼吸器に囲まれた状況で、「今、何ができるのだろう?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、私たちがここにいるのは、患者さんがこれから良くなる可能性があるからです。私たちが見ているのは、今この瞬間だけではありません。ICUを退室し、退院し、その先の人生をどのように歩んでいけるか。これまでどんな人生を歩んできたのかを知り、その上で未来をどう築けるのかを一緒に考えています。
リハビリの時間が辛かったり、動くのが億劫に感じられたりすることもあるかもしれません。しかし、その一歩一歩が未来をより良くするための大切な土台になると、私たちは確信しています。
「希望があるから私たちがいる」
私たちの役割は、患者さんとご家族が未来を描くお手伝いをすること。その未来が少しでも明るいものであるよう、心と身体の両方に寄り添いながら、全力でサポートさせていただきます。

患者さんやご家族にとって、ICUでの時間は不安でいっぱいだと思います。鵜澤さんの「希望があるから私たちがいる」という言葉は、多くの方の心を支える力強いメッセージだと感じました。
リハビリテーションは、身体の回復だけでなく、心と身体の「しなやかさ」を育み、未来への希望を紡ぐプロセス。鵜澤さんのお話を伺いながら、その深い意味を改めて考えさせられました。
呼吸リハビリテーションの第一線を歩み、多くの患者さんやご家族、そしてチーム・スタッフを支えてこられた鵜澤さん。リハノワはこれからも、鵜澤さんのご活躍を心から応援しています。
本日は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。


<関連記事>
・亀田メディカルセンターリハビリ部門 紹介記事
・【特集】亀田総合病院が力を入れる、注目のリハビリテーション (◀ ICUのリハ紹介記事)
・小柴輝晃さん(腎リハに取り組む理学療法士)取材記事
・須貝朋さん(産後リハに取り組む理学療法士)取材記事
・宮本瑠美さん(スポーツ医科学センター/トレーナー)取材記事
・上村尚美さん(リハビリ病院/作業療法士)取材記事
・長尾圭祐さん(リハビリ病院/言語聴覚士)取材記事
・渡慶次かおりさん(総合病院/言語聴覚士)取材記事
ぜひ合わせてご覧ください。

以上、今回は千葉県鴨川市にある亀田総合病院で呼吸領域のリハビリテーションに携わる、理学療法士で米国呼吸療法士の鵜澤吉宏さんを紹介しました。
ひとりでも多くの方に、鵜澤さんの素敵な想いと魅力がお届けできれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今後ともリハノワをよろしくお願いいたします!
かわむーでした。

この取材は、本人から同意を得て行なっています。本投稿に使用されている写真の転載は固くお断りいたしますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
リハノワは、株式会社Canvas、他パートナー企業、個人サポーター、読者の皆さまの応援のもと活動しています。皆さまからのご支援・ご声援お待ちしております。
※取材先や取材内容はリハノワ独自の基準で選定しています。リンク先の企業と記事に直接の関わりはありません。





コメント