みなさんこんにちは、リハノワのかわむーです!
今回は、沖縄県石垣市を拠点に、放課後等デイサービスの運営やオンラインを活用した言語聴覚療法(オンラインST)の普及に取り組む、言語聴覚士の矢崎真一さんにお話を伺いました。
「ないなら、自分で作る」。そんな想いで、地域に必要な支援を形にしてきた矢崎さん。この記事では、支援の枠を超え、新たな常識を築く挑戦を続ける矢崎さんの取り組みと、これから描く未来についてご紹介します。
取材日:2024年12月
言語聴覚士・矢崎真一さん

◆ 矢崎 真一 (やさき・しんいち)さん
言語聴覚士 / 自立活動教諭[言語] / 特別支援教育士 / 公認心理師
1960年生まれ、三重県鳥羽市出身。大阪大学基礎工学部を卒業後、エンジニアとしてのキャリアを歩むも、「ことば」や「コミュニケーション」と向き合う仕事への関心から言語聴覚士を志し、国立障害者リハビリテーションセンター学院の言語聴覚学科へ進学。37歳で言語聴覚士として病院勤務を開始。2003年、石垣島へ移住。現地で生まれた息子がダウン症を持っていたことをきっかけに、子どものリハビリテーションにも力を注ぐようになる。2011年に合同会社ファーストハンドコミュニケーションを設立し、代表社員に就任。現在は放課後等デイサービスの運営や訪問支援を行うほか、オンラインを活用した言語聴覚療法など、新たな形のリハビリテーション支援にも取り組んでいる。

現在は石垣島を拠点に、障害をもつお子さんの支援やオンラインでのリハビリテーションの普及に力を注がれている矢崎さんですが、もともとはエンジニアとしてご活躍されていたと伺いました。言語聴覚士(Speech Therapist:ST)を志したきっかけや、資格取得後の歩みについてお聞かせください。

大学時代、脳性麻痺や自閉症の子どもたちと関わる機会があり、その頃から「ことば」や「コミュニケーション」を支える仕事に強く惹かれていました。
一度はエンジニアとして大阪などで働いていましたが、「やはり人のことばを支える仕事がしたい」という思いが強まり、32歳で会社を退職。1年間アルバイトをしながら勉強を続け、国立障害者リハビリテーションセンターを受験し、翌年合格しました。
37歳で言語聴覚士の免許を取得し、千葉県鴨川市にある亀田総合病院に就職。急性期の医療現場で約2年間経験を積んだ後、ご縁があり、国際医療福祉大学言語聴覚学科で教育に携わることになりました。
石垣島での挑戦のはじまり

大学での勤務を経て、2003年に石垣島へ移住されたそうですが、そのきっかけは何だったのでしょうか? 移住後の働き方についてもぜひお聞かせください。

きっかけは、娘の喘息でした。4歳だった娘が寒くなると発作を起こすようになり、「暖かい場所なら症状が落ち着くのでは」と考えたんです。そんなとき、ふと石垣島のことを思い出しました。
ちょうどその頃、僕の2つ下の後輩が石垣島で働いていたのですが、退職することになり、「じゃあ僕が行く」と手を挙げました。妻が妊娠中でしたが、不安よりも「行こう」という気持ちのほうが強かったですね。
そして、石垣島で生まれた息子はダウン症をもっていました。もし事前に分かっていたら、移住を決断できていたかどうかは分かりません。でも、振り返ると、この島での暮らしがいまの自分の活動につながっているのは間違いないと感じています。
石垣島では、まず「かりゆし病院」で勤務し、主に成人のリハビリテーションを担当しました。
5年半の勤務のうち、3年間は八重山地域で唯一のSTとして働いていました。他の病院に入院している方も、外来で僕のもとへ通ってくるような状況で、島全体のSTのリハビリを担っているような感覚でした。

3年間も八重山諸島で唯一の言語聴覚士として活動されていたとは…! まさに地域にとって欠かせない存在だったのですね。そんな中、病院を退職し、障害をもつお子さんの支援に特化した施設を立ち上げようと決意されたのは、どのようなきっかけだったのですか?

ダウン症の息子が小学校に入るタイミングで、療育的な支援がまったくないことに気づいたんです。一応、社協(社会福祉協議会)が運営する預かり施設はありましたが、リハビリ的なアプローチはされていませんでした。
「ないなら、自分で作ろう!」と思ったのが、新たな挑戦のはじまりでした。
とはいえ、最初から大きな施設を作るのは難しかったので、まずはSTとして開業してみることにしました。STの支援ができる部屋を借り、4回7500円という、できるだけ負担を抑えた料金設定で自費診療をスタート。
しかし、経済的に通い続けるのが難しい方もいらっしゃり、支援を届けたくても限界があることを痛感しました。収入面でも厳しく、週に1回半日だけ病院でアルバイトをしたり、障害者入所施設で週に3時間だけ働いたりしながら、なんとかやりくりしていました。
そうした試行錯誤を重ねながら2年間フリーランスで活動し、2011年に合同会社「ファーストハンドコミュニケーション」を設立。児童デイサービス「ファーストハンド」を立ち上げ、石垣島で言語聴覚士による療育支援を本格的にスタートさせました。

子どもたちの自立を目指して

支援が足りないと感じたときに諦めるのではなく、「ないなら、自分で作ろう!」と行動に移す矢崎さんの姿勢に、強い信念と情熱を感じました。
児童デイサービスの立ち上げ後、どのように事業を展開されていったのでしょうか? その後の歩みや、支援の広がりについてもぜひお聞かせください。

2011年に児童デイサービス「ファーストハンド」を立ち上げた当初は、病院の外来で診ていた子どもの数を考えても、「この規模でなんとかなるだろう」と思っていました。
ところが、実際に運営を始めてみると、想像以上に課題が多く、すぐに限界を感じることになります。
当時の石垣島には、子どもたちが継続的に言語訓練を受けられる場がなく、支援は週に1回、20分程度しか提供できない状況でした。
これでは十分な支援を届けるのは難しいと感じ、翌2012年に高学年向けの放課後等デイサービス「ファーストハンドHi」を新たに開設。さらに2013年には、幼児向けの「ファーストハンドチルダ」を開設しました。
しかし、ファーストハンドチルダの方は、重度の障害があっても多くの子どもたちは保育所に通うことができていたため、想定していたほど利用が広がりませんでした。そこで、STのクリニック的な機能をもたせた、多機能型通所支援「ウィズトークス」へと切り替えました。
2024年春には、人員の入れ替わりもあり、3つの施設を1つの拠点「ステップス」に統合。これにより運営がスリム化され、スタッフの負担が軽減。その分、保育所や訪問支援にも人員を派遣できるようになり、支援の幅が広がりました。
訪問支援を広げたことで、現在は地域のさまざまな支援機関とのつながりも深まっています。

必要に応じて形を変えながら、支援の場を広げてこられたのですね。地域のニーズに寄り添いながら、柔軟に対応されているのが印象的です。
施設には、どのようなお子さんが通われているのでしょうか? 支援の内容や施設ならではの特徴についても教えてください。

通ってくる子どもたちは、発達障害をもつお子さんが多く、言葉が出づらい子、自閉症の子、集団行動が苦手な子など、特性はさまざまです。
また、ダウン症などの知的障害をもつ子どももいます。身体障害の子どもたちの受け入れも行っていますが、新たな施設が2階になったことで、どうしても対応が難しいケースも出てきているのが現状です。
施設を運営するうえで、僕たちが大切にしているのは「子どもたちの自立につながる支援」です。
自立といっても、すべてを一人でできるようになることではなく、「その子がもっている力を最大限に発揮し、社会の中で生きていけること」と考えています。
そのため、ただ楽しく過ごす場を提供するのではなく、「できることを増やす」ことを意識しています。
たとえば、年長さんから小学4年生の子どもを対象としたクラスでは、グループワークを中心に行い、ルールに沿った活動を大切にしています。「椅子に座る」「名前を呼ばれたら返事をする」といった、集団の中で必要な行動を学んでいく機会をつくっています。
「この子には難しい」と思われがちなことでも、環境を整え、適切に関わることで、子どもたちはきちんとできるようになっていくんです。

成長が希望の輪を広げる

その子が持つ力を最大限に伸ばし、「できることを増やしていく」という考え方が、とても素敵ですね。
開所後、矢崎さんの息子さんも施設に通われていたかと思いますが、現在はどのような生活を送られているのですか?

息子は高校1年生のとき、発達年齢は5歳6ヵ月ほどでしたが、地元の定時制高校に進学しました。商業科だったので、簿記などの授業は難しいかなと思っていましたが、学校側が特別支援のカリキュラムを作ってくれたおかげで、3年間で無事に卒業。その後、沖縄本島の専門学校に学校推薦で進学し、2年の学びを経て卒業しました。
現在はひとり暮らしをしながら、短時間のアルバイトをしています。今年で成人を迎え、ひとり暮らしも3年目になります。
最初は親としても心配でしたが、大きなトラブルや事故もなく、自分の力で生活できていることを考えると、本当に成長したなと感じます。
もちろん、すべての子が同じ道を歩めるわけではありませんが、それぞれのペースで成長し、自分らしく生きていける可能性を広げることが大切だと思っています。これからも、そうした支援を続けていきたいですね。

お子さんの将来について不安を抱える保護者の方も多いと思うので、矢崎さんの息子さまが自立して生活されている姿は、きっと多くの方の「希望の光」になっていると感じました。
矢崎さんが子どもたちの支援をするうえで、特に大切にしていることは何ですか? また、日々の取り組みの中で感じる課題や難しさなどもあれば、ぜひお聞かせください。

子どもたちの支援に関わる中で、最近とくに感じるのは、「障害児」という枠に入れられる子どもたちが増えていることです。特別支援学級に通う児童も年々増えており、それが本当に必要な支援につながっているのか、考えさせられる場面もあります。
特別支援学級への進学は、診断が前提ではなく、保護者の希望と教育委員会の判断によって決まります。以前なら、周囲に励まされながら成長し、次第に落ち着いていった子どもたちも、今は早い段階で特別支援の枠に入ることが増え、そのまま進学や就職の選択肢が限られてしまうケースもあります。
もちろん、支援が手厚くなることで安心できる部分もありますが、一方で、子どもたちの可能性が広がる機会を失ってしまうことがあるのでは、と感じることもあります。
支援が必要な子どもたちが適切なサポートを受けられることは大切ですし、それぞれの成長のペースに寄り添うことが重要です。ただ、その子が本来持っている力を引き出し、できることを増やしていける関わり方も、同じくらい大切だと考えています。
「自分は特別扱いされる存在ではない」「自分もできることを増やしていこう」といった意識を育むことは、学びのプロセスそのものです。その積み重ねが、子どもたちの未来をより豊かにしていくのではないかと思っています。

オンラインSTの可能性

ここからは、矢崎さんが取り組まれている、オンラインを活用した「遠隔リハビリテーション」についてお話を伺いたいと思います。
離島が多い八重山地域では、特にこうした支援のニーズが高いのではないかと感じますが、この取り組みを始められたきっかけや、これまでの歩みについて教えていただけますか。

オンラインを活用した支援は、2005年頃からはじめました。
当時はスカイプとADSLを使い、最初のきっかけは西表島西部に住む知人のお父さんへのサポートでした。「何かできることはないか」と相談を受け、試しにオンラインでつないで支援を行ったのが始まりです。
また、その頃、僕は沖縄の専門学校で非常勤講師として失語症の授業を担当していました。学生たちは「患者さんと接したことがない」と話していたので、オンラインで実際の患者さんとつながせてもらい、実習的な形でやりとりを経験してもらいました。これも、オンライン支援の可能性を感じた経験のひとつです。
その後、与那国島に機能性構音障害のあるお子さんがいて、「小学校に入るまでに発音を改善したい」という相談を受けました。ただ、ご自宅にはネット環境がなかったため、与那国町役場の職員さんの机まで来てもらい、そこでオンラインをつなぎリハビリを行いました。
こうした活動を続ける中で、オンラインを活用した効率的な支援の方法が少しずつ見えてきました。
その後、セラピスト仲間たちとともに「八重山諸島リハビリテーション支援ユニット・やーるー」という任意団体を立ち上げ、八重山の各島を巡る体操教室を実施しました。ちょうどその頃、竹富町の課長さんが活動に協力的で、ネット環境の整備を進めてくださり、パソコンやプロジェクター、スクリーンを活用したオンライン体操教室を試験的に実施。2008年には、年に3回ほどこの取り組みを行うことができました。
現在も、与那国島、竹富島、波照間島、西表島など、それぞれの島で試行錯誤を重ねながら活動を続けています。
与那国島や波照間のように、冬は一度行くと帰れるかどうか分からないような場所もあり、移動の負担も大きいのが現状です。こうした環境だからこそ、オンライン支援の可能性を改めて実感しています。


とくにSTは、オンラインとの相性が良い職種だと感じています。
そこで、2022年には「オンラインST研究会」という団体を立ち上げました。ここでは、オンラインSTの技術的な基盤づくりやエビデンスの蓄積、言語聴覚士の育成に加え、保険制度や行政との連携についても議論を深めながら、多くの方々とつながり、支援の可能性を広げる取り組みを進めています。
アメリカでは、2000年代中盤にはすでにSTと利用者をつなぐシステムがいくつも存在していました。STにあたるSLP(Speech-Language Pathologist)が学校に配属されていることが多く、SLPがいない学校ではオンラインでつなぎ、先生が子どもを連れてきてオンライン支援を受ける仕組みが確立されています。
日本でも、こうした仕組みを取り入れることで、より多くの子どもたちが継続的な支援を受けられる環境を整えていけたらと考えています。
新たな常識を築く挑戦

コロナ禍を経て、オンラインでのやりとりに対する抵抗感が減り、活用の幅も広がってきたように感じています。そうした変化を、どのように捉えていらっしゃいますか?
また、今後取り組んでいきたいことや、新たにチャレンジしたいことがあれば、ぜひお聞かせください。

コロナ後、ヨーロッパではオンラインSTが当たり前になり、アメリカでも子ども向けのST支援の多くがオンラインに移行したといわれています。
しかし、日本ではまだ普及が進みにくい状況があります。特に、自費診療という点が影響し、「サービスを受けるためにお金を払う」という意識が根づいていないことが、広がりを妨げる要因の一つだと感じています。
オンラインSTを推進するためには、著作権の問題や技術面の整備など、クリアすべき課題も多くあります。そのため、昨年は助成金を活用し、IT企業のサポートを受けながら、オンライン支援に活用できるシステムの開発に取り組みました。質の高い支援をオンラインでも提供できるよう、デジタルツールの整備は不可欠だと考えています。
また、全国に約3万人のSTがいるものの、小児領域に関わるのは約3000人ほどしかいません。STの数を急に増やすことが難しい中で、「STのスキルをもつ支援者を増やす」ことも重要だと考えています。
その一環として、「親御さんへのオンラインサポート」をもっと充実させ、より多くの家庭に継続的な支援を届けることにも力を入れていきたいと思っています。
STの約8割は女性で、結婚や出産を機に一時的に家庭に入る方も多いですが、その間もオンラインで働くことができれば、支援の継続につながります。オンラインの活用は、支援の質を高めるだけでなく、支援者の働き方の選択肢を広げる可能性も秘めています。
今後も、より柔軟で持続可能な支援の仕組みをつくるために、オンラインSTの普及を進めていきたいと考えています。

リハビリテーション全般にいえることですが、関わっている時間だけで対象者が大きく変わることは難しい。だからこそ、日常の中でどれだけ積み重ねられるか、そのために周囲の人たちをどう巻き込んでいくか。そうした視点が、対象者の可能性を大きく広げていくことにつながるのですね。
矢崎さんのお話を伺いながら、「ないなら、自分で作る」というその柔軟な発想と行動力が、子どもたちの未来を支え、地域に根ざした新しい支援の形を生み出しているのだと感じました。
石垣島での療育支援の立ち上げだけでなく、オンラインSTの可能性を広げる矢崎さんの挑戦を、リハノワはこれからも応援しています。
本日は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。
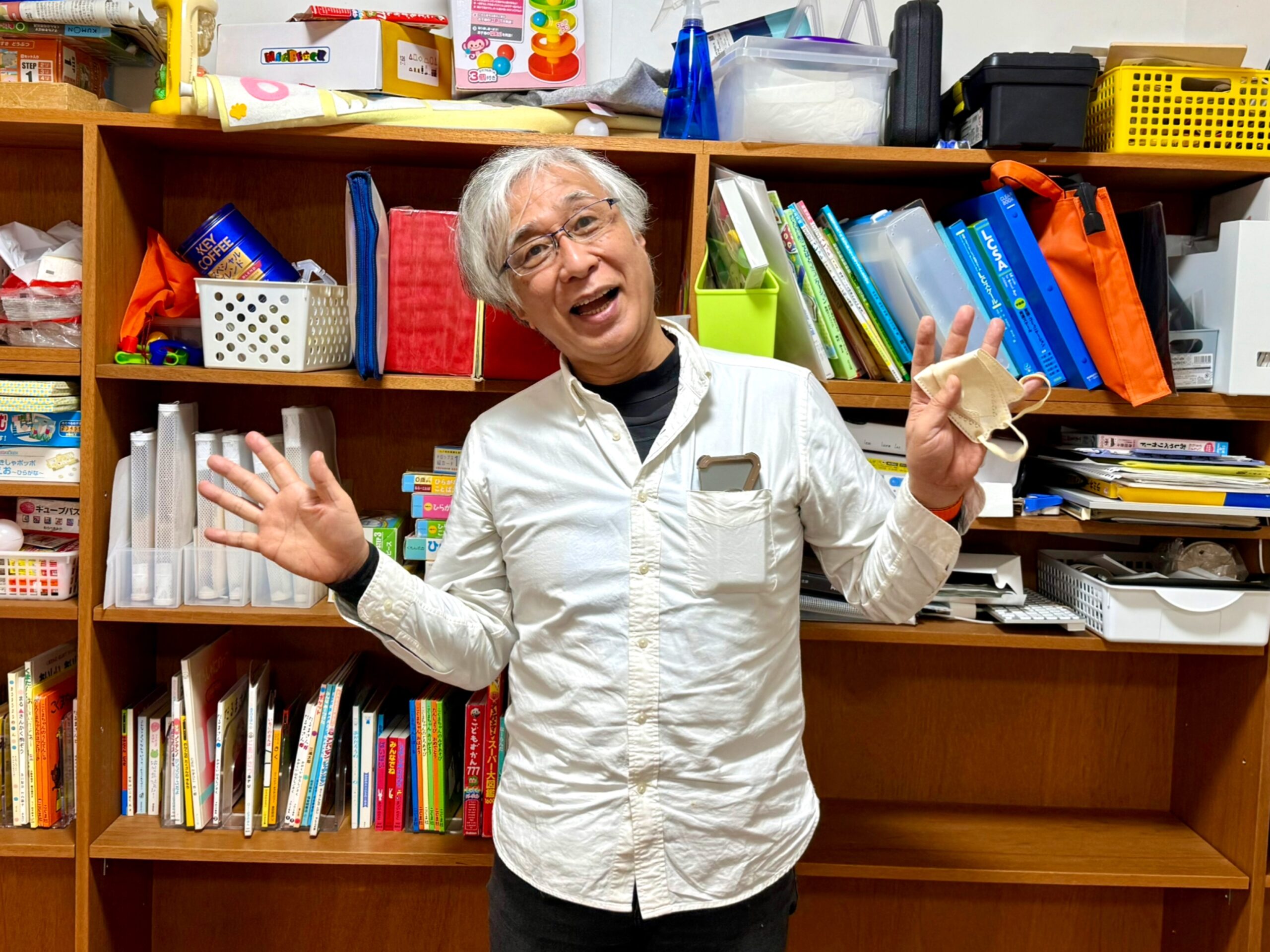

<関連記事>
・石垣島で活動する言語聴覚士・池田あかねさん
・デイサービス「JOYいしがき」|沖縄県石垣市
・Coco-on共同代表/言語聴覚士・知念洋美さん
・【当事者の声】オンラインSTを受講したはるくんとお母さん
<関連サイト>
・一般社団法人Coco-on ホームページ
・オンラインST研究会 ホームページ
ぜひ合わせてご覧ください。

以上、今回は沖縄県石垣市を拠点に、放課後等デイサービスの運営やオンラインSTの普及に力を注ぐ言語聴覚士・矢崎真一さんをご紹介しました。
これまで代表を務めていた「ファーストハンドコミュニケーション」の全事業は、2025年4月よりSmartStudyに引き継がれ、現在は「ジョイーレいしがき」のスタッフとして、変わらぬ情熱で子どもたちと向き合っていらっしゃいます。
また、矢崎さんは、「一般社団法人Coco-on」の共同代表や、「一般社団法人 八重山地域リハビリテーション支援ユニット(やーるー)」の役員、「オンラインST研究会」の世話人としてもご活躍中です。言葉を軸に、人と人とのつながりを広げていくその姿は、多くの方の希望になっています。
この記事を通じて、矢崎さんのあたたかな想いとまっすぐな歩みが、ひとりでも多くの方に届いていたらうれしいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今後ともリハノワをよろしくお願いいたします!
かわむーでした。

この取材は、本人から同意を得て行なっています。本投稿に使用されている写真の転載は固くお断りいたしますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
リハノワは、株式会社Canvas、他パートナー企業、個人サポーター、読者の皆さまの応援のもと活動しています。皆さまからのご支援・ご声援お待ちしております。
※取材先や取材内容はリハノワ独自の基準で選定しています。リンク先の企業と記事に直接の関わりはありません。


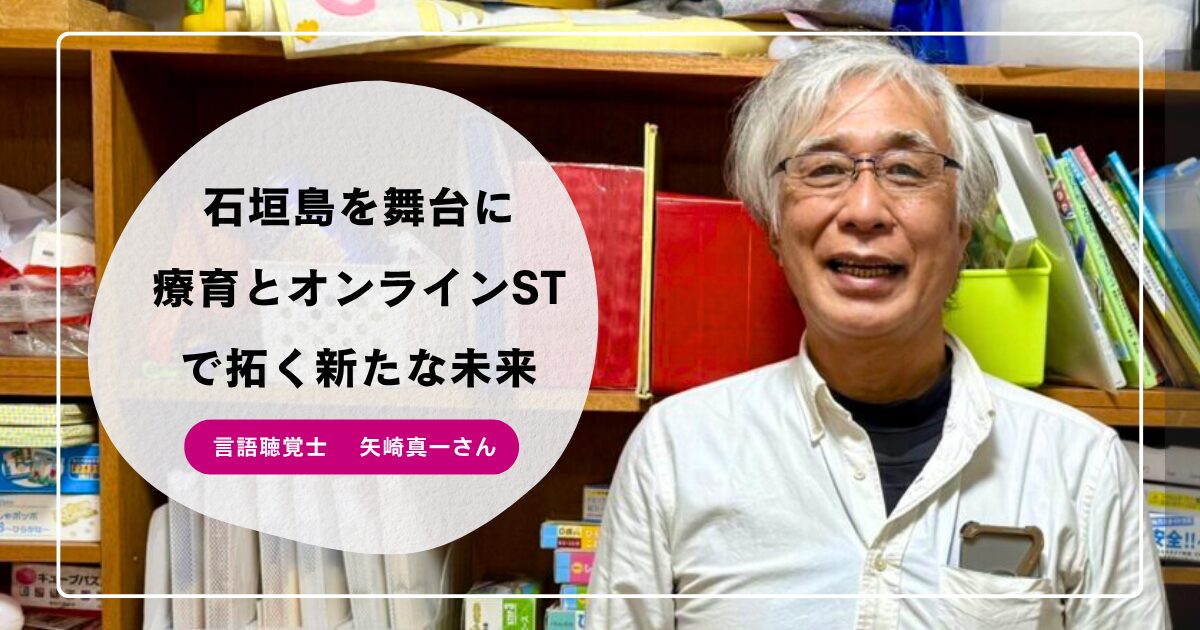


コメント