2024年12月、オーストラリア・メルボルン。自閉症支援に特化したリハビリテーション施設で働く、日本人作業療法士・沖田勇帆さんを訪ねました。
高校卒業後、単身でオーストラリアへ渡り、語学学校、大学、作業療法士の修士課程を経て、現地で資格を取得。現在は、リハビリテーション部門のマネジメントを担いながら、地域の子どもたちやご家族に寄り添う支援に情熱を注いでいらっしゃいます。
「オーストラリアで働く作業療法士は、どんなふうに働いているんだろう?」そんな素朴な問いから始まった今回の取材は、キャピタルメディカ・ベンチャーズ様のご協力のもと、実現しました。
この記事では、沖田さんへのインタビューや、実際の現地での体験から見えてきた、オーストラリアでの作業療法士の働き方についてご紹介します。
※沖田さんの個別インタビュー記事も、あわせてご覧ください(記事下部にリンクあり)
OT沖田勇帆さんインタビュー
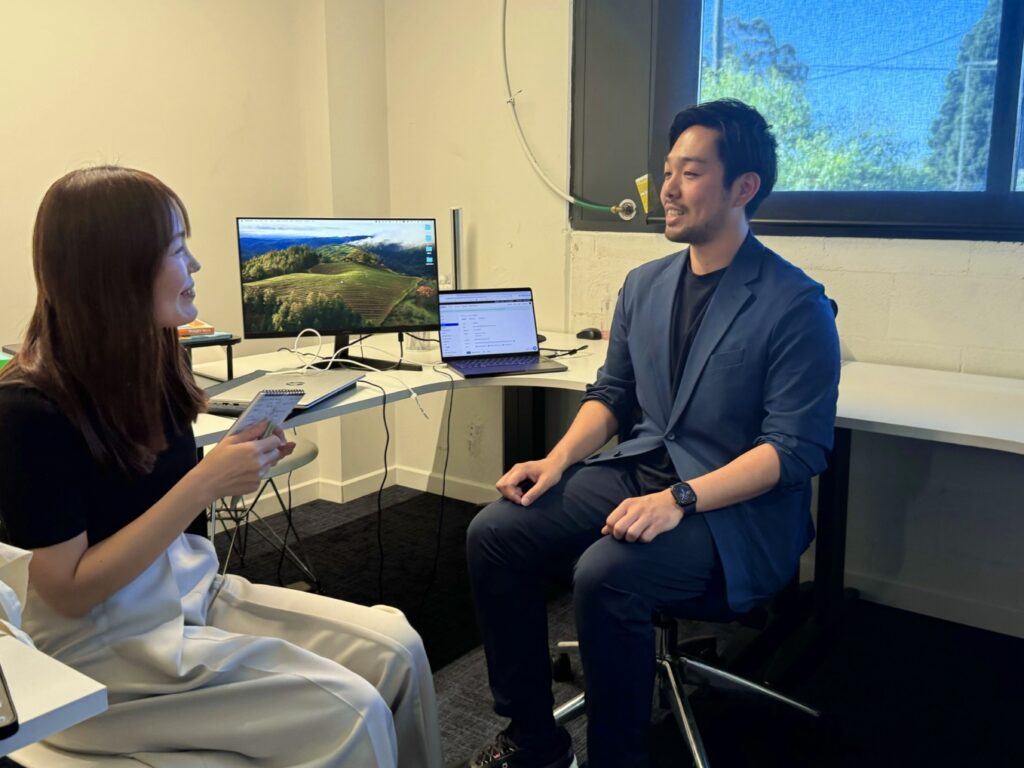
オーストラリアのOTの現状

はじめに、オーストラリアの作業療法士(Occupational Therapist:OT)のみなさんについて、現状や、実際の働き方について教えていただけますか?

まず、作業療法士の人数についてですが、オーストラリアには現在、約30,000人の作業療法士が登録されています(2023年 AHPRA登録者数※)。男女比はおよそ1対9で、女性が圧倒的に多いのが現状です。
働く場所については、日本と同じように病院で勤務されている方もいらっしゃいますが、その割合は決して多くありません。2020年のデータでは、外来を除いた病院勤務は、全体の2割ほどといわれています。
オーストラリアでは、作業療法士・理学療法士・言語聴覚士のいずれの職種も、医師の指示がなくても自らの判断で評価や介入を行い、保険請求をすることができます。そのため、個人で開業したり、複数の専門職と一緒にチームを組んで活動したりするセラピストも多くいます。
また、オーストラリアでは「病院は医療の場であって、長く滞在する場所ではない」という考え方が一般的です。治療がひと段落したら、できるだけ早く在宅や施設、地域のサービスへとつなげる、という流れが基本になっています。
たとえば、脳卒中の方の場合、日本では長期的なリハビリ入院を経て、自宅や施設へと退院するケースが多くみられますが、オーストラリアでは急性期から回復期を含めても平均2週間ほどで退院します。その後は、訪問リハビリや外来リハビリなど、地域に戻ってからの支援が中心となります。
地域に戻った後のサポートで大きな役割を担っているのが、NDIS(National Disability Insurance Scheme)という障害者保険です。障害のある方が地域で安心して暮らしていくために、必要なサービスを受けられるようサポートする制度です。
作業療法士は、NDISのケアプランを策定する際に必要となるレポートを担当します。レポートは、「機能的能力評価」に基づいて作成されます。
実際に患者さんと一緒にリハビリをする時間だけでなく、こうした評価やレポート作成にかなり時間をかけていることも、オーストラリアの作業療法士として働く上で特徴的な点の1つかもしれません。
※ AHPRAとは?
AHPRA(Australian Health Practitioner Regulation Agency / オーストラリア医療従事者規制庁)は、すべての登録医療従事者の「質・安全・倫理」を守ることを目的に、2009年に設立された公的機関です。リハビリ職種では、理学療法士と作業療法士が登録を義務づけられています。
一方、言語聴覚士には登録の義務はなく、多くの方が職能団体であるSpeech Pathology Australia(SPA)に所属し、活動しています。

オーストラリアでは「できるだけ早く暮らしの場に戻る」ことが、社会や文化のなかにしっかり根づいているのですね。NDISという制度のあり方や、作業療法士さんの働く場所や役割にも、その空気をとても強く感じました。
オーストラリアといえば「労働者保護が手厚い国」ともいわれていますが、実際に作業療法士として働く中で、職場環境や働きやすさについてはどのように感じていらっしゃいますか?

リハビリテーション業界も例外ではなく、働きやすさについては「とても良い」と感じています。
プライベートと仕事の両立、いわゆるワークライフバランスが大切にされる文化が醸成されているので、遅くまで残業をしたり、土日に働いたりすることはほとんどありません。病院でも、土日にリハビリを提供しているところは多くない印象です。
この背景には、時間外や土日・祝日に働く場合は給料をしっかり上乗せしなければならないというルールがあるので、経営的にも「無理をさせてまでやらない」という事情もあるかと思います。
それから、日本と大きく違うと感じるのが、スタッフの身体的な負担を減らすための仕組みです。
医療・介護・福祉の現場では、腰痛予防や身体への負担軽減のため、移乗介助の際にはリフト(昇降機)の使用が義務づけられていたり、強く推奨されていたりします。
このあたりも、働く人を守るための文化や仕組みがしっかり整っているなと感じる点の1つです。

オーストラリアの「働きやすさ」は、やはり本当だったのですね。メルボルンを訪れた際、夕方5時を過ぎると街に多くの人があふれ、食事やお酒を楽しむ姿がとても印象的でした。訪れた12月末は、外が夜9時ごろでも明るく、街全体がどこか開放的で、活気に満ちた空気を感じたのを覚えています。オーストラリアで働く人たちが、無理をしすぎず、自分の暮らしも大切にしながら働いている様子が伝わってきました。
また、移乗の場面でリフトを使うことが当たり前になっている、というお話には、正直、驚きました。私自身、臨床時代は腰痛に悩まされた時期もありましたし、周りにも腰痛を抱えながら働く仲間がたくさんいました。日本では「人力で支えること」が当たり前ですが、オーストラリアではそれがリスクとして扱われることもある。改めて、「支える人」も「支えられる人」も、どちらも大事にする文化に学ばせていただく思いです。
ここまで、働き方についていろいろとお話を伺ってきましたが、やっぱり気になるのはお金のこと。実際に作業療法士として働くうえで、収入や生活費の面はいかがでしょうか?

収入については、経験年数や働く場所、雇用形態によって大きく変わるので一概にはいえませんが、日本と比べると、およそ1.5倍から2倍くらいをイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。
その一方で、出費もそれなりにあります。とくに家賃は、住む場所などによって差はありますが、全体的には日本より高い印象です。ひとり暮らしでも、月に十数万円から20万円くらいは見ておいたほうがいいかなという感じです。
電気代や水道代などの公共料金、インターネット料金は、日本とそれほど大きな違いはありません。食費についても、自炊を中心にすれば、そこまで大きな負担にはならないという感覚です。

たしかに、飲食店は全体的に日本よりもお値段が高い印象でしたが、スーパーに並んでいるお肉やお魚、野菜は、日本とそれほど変わらない価格だなと感じました。
収入面では日本よりも恵まれているように思いますが、実際には、家賃や生活コストとのバランスをどう整えるかが大切なんですね。リアルなお話をお聞かせいただき、ありがとうございます。




沖田さんの働き方


沖田さんは、2024年10月から、メルボルンにある自閉症支援を専門とする施設「Autism Abilities」でご勤務されています。
ここからは、沖田さんの現在の職場のこと、そして実際にどのようにお仕事をされているのか、ぜひ詳しくお聞かせいただけますでしょうか。

「Autism Abilities」は、2018年にメルボルンで設立された、自閉症支援に特化した施設です。「すべての自閉症の人が充実した人生を送れるように」というミッションのもと、作業療法や言語聴覚療法、ポジティブ行動支援(Positive Behavior Support:PBS)など、さまざまなサービスを提供しています。
また、個別の支援だけでなく、ご家族や学校、地域コミュニティに向けたワークショップやトレーニングも行っています。
僕はここで、アライドヘルスサービスマネジャーとしてリハビリ部門の立ち上げを任され、多職種のチームづくりやマネジメントを担当しています。
現在のチーム体制は、作業療法士3名と言語聴覚士1名ですが、2025年末までには、どちらも4名ずつに拡充していく予定です。
リハビリの対象となる方は、2歳ほどの小さなお子さんから60代までと幅広く、支援の方法も、外来だけでなく、ご自宅や学校への訪問、オンラインでのリハビリなど、それぞれのニーズにあわせて柔軟に対応しています。



当施設では、NDISを利用している方々を多く対象としています。NDISは、支援の料金が1分単位で設定されていて、1時間あたりのレートは約194豪ドル(日本円で18,000〜19,000円ほど)です。
ちなみに、訪問リハビリにかかる移動時間も、支援時間として正当に認められています。日本では報酬対象外(事業者側の負担)ですが、オーストラリアでは「利用者にサービス提供するために必要なコスト」として、請求できる仕組みがあります。たとえば、20分かけて自宅に伺い、40分リハビリを提供した場合、その移動時間も含めた1時間分をNDISから請求できるイメージです。移動にかかる費用も同様です。
リハビリの頻度や期間は、NDISから支給される給付金の範囲内で決まるため、週1回の方もいれば、2週に1回の方もいらっしゃいます。
支援のスタート時には、まずセラピストとの初回面談を行い、クライアントさん一人ひとりに合わせたリハビリプランを丁寧に組み立てていきます。
僕自身の働き方としては、朝9時に始業し、夕方5時までが営業時間です。施設での診療や管理業務などを行いながら、訪問に出ることもあります。

オンラインでの診療・連携

オーストラリアでは、遠隔でのリハビリテーションも日常的に実施されているのですね。国土が広く、医療機関やリハビリテーション施設が限られていることも、背景にあるのでしょうか。
日本では、制度や環境の整備がまだ十分とはいえず、遠隔リハビリテーションは「これから広がっていく可能性がある」という印象をもっています。実際にオーストラリアで遠隔リハビリテーションを実践されてきた中で、どんな手応えや気づきがあったか、ぜひお聞かせいただけますか?

オーストラリアでは、遠隔でのリハビリテーションがすっかりスタンダードになっています。NDISの対象でもあり、対面との料金の差もないため、体調や予定に合わせて、「今日はオンラインでお願いします」と当日に切り替える方もいらっしゃいます。
電話やWeb会議ツールを使って行うのですが、1時間しっかりセッションを行うこともあれば、体調やご家庭の都合に合わせて、15分ほどの電話相談にすることもあります。状況に応じて柔軟にサポートできるのが大きな魅力です。
リハビリテーションに対する考え方そのものも、日本とは少し違うのかもしれません。オーストラリアでは、「直接触れて治療すること」がすべてではなく、オンラインでのかかわりも、立派な支援の1つとして受け入れられている印象です。
日本では、「ビデオ越しで何ができるの?」と、まだまだネガティブに捉えられてしまうこともあるように感じますが、こちらでは対面と同じように、有効な手段の1つとして活用されています。
また、医療・介護・教育など、さまざまな関係機関との連携も、オンラインが当たり前になっています。
たとえば、病院からの退院時には、リハビリスタッフや医師、ご家族、学校の先生などが集まり、「ケアチームミーティング」がオンラインで開かれます。そこで、チーム全員でこれからの支援について話し合う場がしっかりと設けられています。


遠隔リハビリテーションを「特別なもの」としてではなく、「当たり前の選択肢のひとつ」として自然に活用しているのが印象的でした。
日本にも、島しょ部や人口減少が進む地域がたくさんあります。遠隔支援の制度や技術は少しずつ整いつつありますが、それを「ひとつの支援のかたち」として受け入れるマインドも合わせて、もっと広がっていくといいなと感じました。
沖田さん、貴重なお話をお聞かせいただき、本当にありがとうございました。

◆ 沖田勇帆(おきた・ゆうほ)さん
長崎県長崎市出身。高校卒業後の2011年、オーストラリア・シドニーへ渡り、語学学校と大学準備コースを経て、2014年にグリフィス大学の運動科学コースへ進学。2016年からは同大学の優等学位コースに進み、研究に携わる。2017年にはメルボルンにあるスウィンバーン工科大学大学院に進学し、作業療法士養成プログラム(修士課程)を受講。2019年7月、オーストラリア医療従事者登録機関(AHPRA)に作業療法士として登録され、資格を取得。同月、メルボルンにある民間のヘルスセンターに入職し、作業療法部門の立ち上げを担当。2021年には同社で研究教育部門を新設し、スウィンバーン工科大学の学費全額免除奨学金に採択され、保健学系大学院博士課程に進学。慢性疼痛と遠隔リハビリテーションをテーマとした研究に取り組む。2024年10月、自閉症支援を専門とする施設(Autism Abilities)に参画。現在は、アライドヘルスサービスマネジャーとしてリハビリテーション部門の立ち上げと多職種チームのマネジメントに力を注いでいる。
■ 施設名:Autism Abilities
■ 設立:2018年
■ 営業時間:月~金 9:00~17:00
■ 所在地:101/1 Olive York Way, Brunswick West VIC 3055
■ お問い合わせ
・電話:1300-324-917 または 0481-112-928
・メール:hello@autismabilities.com.au
■ 関連ページ
・HP・Instagram・Facebook・Linkedin

リハビリテーションを支える仕組み

ここからは補足として、オーストラリアの社会保障制度やリハビリ職種の免許取得について紹介します。
社会保障制度
リハビリテーションの対象となる方を支える、オーストラリアの代表的な医療保険制度(メディケア)と障害者支援制度(NDIS)を紹介します。
◆ 医療保険:Medicare(メディケア)
1984年に創設された国民皆保険制度です。オーストラリア国民のほか、一部の永住者や特定のビザ保持者を対象に、低額または無料で医療サービスを提供しています。主な財源は、課税所得の2%を納税者から徴収する「メディケア税(Medicare levy)」です。
メディケアでは、かかりつけ医(GP:General Practitioner)の診察費や一部の専門医の診療費、公立病院での入院費が全額カバーされます。さらに、一部の処方薬、心理士や精神科医によるカウンセリング、遠隔医療サービスも対象です。一方で、救急車の利用や歯科治療などは補償の対象外となっています。
◆ 障害者保険:NDIS(National Disability Insurance Scheme)
2013年に創設された社会保険制度で、障害のある人の自立や社会参加の促進を目的としています。対象となるのは、オーストラリア国民のほか、一部の永住者や特定のビザ保持者で、65歳未満で日常生活に支障をきたす重度の障害がある方です。具体的には、知的・身体・感覚・認知・心理社会的な障害を抱える成人や、発達障害のあるお子さんなどが対象です。
オーストラリアでは、約430万人が何らかの障害を抱えており、そのうち約69万人がNDISの支援を受けています(2024年12月時点)。NDISでは、日常生活や社会参加のための支援に加え、スキルの向上や自立を目指すサポート、高額な補助具の提供、住宅や車両の改修など、ひとりひとりのニーズに応じた幅広い支援が行われています。
参照:NDISホームページ、MBS Online、Australia Government Department of Health and Aged Care

日本の国民皆保険と同様に、オーストラリアにも「Medicare(メディケア)」という公的医療保険制度がありまが、日本のように原則自由に病院や専門医にかかれるわけではなく、「GP(General Practitioner)」と呼ばれるかかりつけ医を経由する必要があります。大きな病院を受診する際には、GPからの紹介状が求められるのが一般的だそうです。
また、Medicareは「医療アクセスの最低限を国が保障する」という制度であり、より迅速で充実した医療サービスを求める場合は、民間の医療保険を併用することが推奨されています。医療へのアクセスには、経済力による差が日本よりもはっきり現れているように感じました。
「NDIS」について、日本の障害福祉制度と異なると感じた点は、本人の自立や選択がより尊重されていることです。障害の内容や支援ニーズに応じて、個人ごとに年間予算が配分される仕組みになっており、その額はおおよそ2万〜10万豪ドル(日本円で約210万〜1,050万円)にもなるそうです。
オーストラリアには日本のような介護保険制度はありませんが、政府が運営する高齢者ケアのポータルサイト「My Aged Care」があります。原則として65歳以上で介護支援が必要な人が対象となり、介護サービスの紹介や申請、評価、プランの策定まで一括して行える仕組みが整えられています。

免許取得のステップ
◆ オーストラリアでリハビリ専門職の免許取得を目指す場合
大きく分けて2つのルートがあります。1つは、PT・OTに特化した4年制の学部課程を修了するルート。もう1つは、他分野の学士課程を修了した後、PT・OT・言語聴覚士(ST)を専門とする2年間の修士課程に進むルートです。
PTとOTは、卒業後にAHPRAへの登録を行うことで、臨床での実践が可能となります。STについては、CPSP(認定言語聴覚士)として、SPAに登録することで、NDIS・教育・医療などすべての分野で活動することができます。
◆ 日本で取得した免許をもとにオーストラリアで登録を目指す場合
まずは、資格認証機関への申請が必要です。PTはAustralian Physiotherapy Council(APC)、OTはOccupational Therapy Council(OTC)、STはSpeech Pathology Australia(SPA)がそれぞれ担当機関となります。その後、英語力の証明や知識・臨床スキルの評価試験を経て、PTとOTはAHPRAへの登録、STはSPAによるCPSPの認定を受けることになります。
このような過程を経て、オーストラリアで正式にリハビリ専門職として働くことができます。

オーストラリアの基本情報
・首都:キャンベラ
・人口:約2,730万人(2024年9月時点)
・平均年齢:39歳(2024年9月時点)
・高齢化率:17.1%(2022年時点)
・障害のある人:約550万人(21.4%)(2022年時点)
・平均年収(中央値):約67,600豪ドル(週あたり1,300豪ドル)(2024年9月時点)
・面積:768万8,287平方キロメートル(日本の約20倍、アラスカを除く米とほぼ同じ)
・言語:英語
・民族:アングロサクソン系等欧州系が中心。その他に中東系、アジア系、先住民など
・主要産業(GDP構成比順):第一次産業2.4%、第二次産業27.7%、第三次産業69.9%
農林水産業(2.4%)、鉱業(12.2%)、製造業(5.9%)、建設業(7.5%)、卸売・小売業(8.5%)、運輸・通信業(6.9%)、金融・保険業(7.5%)、専門職・科学・技術サービス(7.8%)など(2023~24年度のGVA産業別シェア、出典:豪州統計局)参照:オーストラリア統計局、外務省ホームページ「オーストラリア連邦」





<関連記事・情報>
・OT沖田勇帆さんインタビュー記事
・沖田さんのSNS・出版物等
ぜひ合わせてご覧ください。

以上、本記事ではオーストラリアで活躍する作業療法士・沖田勇帆さんへのインタビューを通じて、現地での作業療法士の働き方について紹介しました。
言葉も、制度も、暮らしも違う、遠く海を越えた地で、試行錯誤を重ねながら、作業療法の可能性を信じて挑み続ける沖田さんの姿に、私自身もたくさんの気づきと勇気をいただきました。
遠く離れた現場での実践が、私たちに「今ここで、何ができるか」を問いかけてくれている気がします。ここまで読み進めてくださったみなさまが、希望をもって、また一歩、前に進んでいけることを願っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
これからもリハノワをよろしくお願いいたします。
かわむーでした。

この取材は、株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ様協力のもと、本人から同意を得て行なっています。本投稿に使用されている写真の転載は固くお断りいたしますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
リハノワは、パートナー企業、個人サポーター、読者の皆さまの応援のもと活動しています。皆さまからのご支援・ご声援お待ちしております。
※取材先や取材内容はリハノワ独自の基準で選定しています。リンク先の企業と記事に直接の関わりはありません。





コメント